「時間が足りない」「やりたいことがあるけれど、いつも後回しになってしまう」——現代人の多くが抱える悩みではないでしょうか。私たちは1日24時間、平等に与えられていますが、なぜか“時間がある人”と“時間がない人”がいるように感じられます。その違いは、「時間を作る力」にあるのです。
時間は“見つける”ものではなく“作る”もの
まず大切なのは、時間は勝手に空かないということ。私たちは「時間ができたらやろう」とよく言いますが、実際に自然に空く時間なんてほとんどありません。だからこそ、“意識的に作る”という視点が重要になります。
例えば、1日の中で「無意識に使っている時間」を洗い出してみてください。SNSのチェック、なんとなくのネットサーフィン、目的のないテレビや動画の視聴。これらを合計すると、1日に1〜2時間は簡単に生まれるはずです。
タスクに優先順位をつける
時間を作るうえで有効なのが、「緊急ではないが重要なこと」に時間を使うこと。これは、スティーブン・R・コヴィー著『7つの習慣』でも紹介されている概念です。多くの人は、緊急で対応が求められることに追われてしまい、本当に重要なこと(自己投資、家族との時間、健康管理など)に手が回らなくなります。
そのためには、「やらないことを決める」ことも必要です。すべての依頼やお誘いに応える必要はありません。「自分にとっての優先事項は何か?」を見極める目が、時間を生む鍵になります。
朝の時間を味方にする
「早起きは三文の徳」という言葉があるように、朝の時間は非常に価値があります。人間の脳は起床後2〜3時間が最もクリアな状態と言われており、この時間帯に読書や執筆、運動などの“重要だけど後回しにしがちなこと”を取り入れるのがおすすめです。
朝が苦手という人も、就寝前のルーティンを見直すことで自然と早起きがしやすくなります。夜のスマホ時間を減らし、30分早く寝るだけでも翌朝の時間に余裕が生まれます。
「完璧」を目指さない
多くの人が時間を失う理由の一つに、「完璧主義」があります。すべてを丁寧に、すべてを完璧に仕上げようとすると、終わらない、進まない、疲れてしまうという負の連鎖が始まります。むしろ、“80点でOK”というマインドで取り組むことで、結果的に多くのことをこなせるようになります。
小さな積み重ねが大きな時間になる
1日10分の勉強や運動でも、1ヶ月続ければ300分、1年で3,650分、つまり約60時間にもなります。「どうせ10分しかないから」と思わず、「この10分が未来を変える」と捉えることが大切です。時間の使い方に“意味”を与えることで、日常が変わっていきます。
まとめ:時間の質を上げよう
時間は有限でありながら、使い方次第で無限の可能性を秘めています。スマートフォンの通知を切る、予定を詰めすぎない、やらないことリストを作る——ちょっとした工夫で、驚くほどの「余白」が生まれます。
「時間がない」と感じたときこそ、立ち止まって自分の時間の使い方を見直すチャンスです。本当にやりたいこと、大切にしたい人、自分自身の未来のために、今ここから“時間を作る力”を磨いていきましょう。

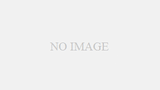
コメント